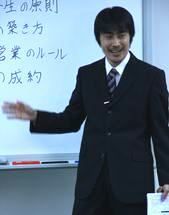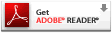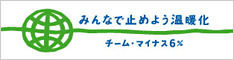(許可申請書等の提出)
第一条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (以下「法」という。)及びこの規則の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所(無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業に係る届出書にあつては、当該営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下この条及び第八十七条において単に「事務所」という。))の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の申請書又は届出書を提出しなければならない。
2 一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所又は事務所について次のいずれかの申請書又は届出書を提出するときは、前項の規定にかかわらず、それらの営業所又は事務所のうちいずれか一の営業所又は事務所の所在地の所轄警察署長を経由して提出すれば足りる。
一 法第五条第一項 に規定する許可申請書
二 第十四条第一項に規定する相続承認申請書
三 第十五条第一項に規定する合併承認申請書
四 第十六条第一項に規定する分割承認申請書
五 法第九条第三項 に規定する届出書のうち、法第五条第一項第一号 又は第六号 に掲げる事項(同項第一号 に掲げる事項にあつては、風俗営業者の氏名又は名称を除く。)の変更に係るもの
六 法第十条の二第二項 に規定する認定申請書
七 法第二十七条第二項 に規定する届出書のうち、店舗型性風俗特殊営業の廃止又は同条第一項第一号 に掲げる事項の変更に係るもの
八 法第三十一条の七第一項 又は同条第二項 において準用する法第三十一条の二第二項 に規定する届出書
九 法第三十一条の十二第二項 において準用する法第二十七条第二項 に規定する届出書のうち、店舗型電話異性紹介営業の廃止又は法第三十一条の十二第一項第一号 に掲げる事項の変更に係るもの
十 法第三十三条第二項 に規定する届出書のうち、深夜における酒類提供飲食店営業の廃止又は同条第一項第一号 に掲げる事項の変更に係るもの
3 前項の規定により二以上の営業所若しくは事務所のうちいずれか一の営業所若しくは事務所の所在地の所轄警察署長を経由して同項各号の申請書若しくは届出書を提出する場合又は一の警察署の管轄区域内にある二以上の営業所について同時に風俗営業者の氏名若しくは名称の変更に係る法第九条第三項 に規定する届出書若しくは法第二十七条第一項 、第三十一条の十二第一項若しくは第三十三条第一項に規定する届出書を提出する場合において、これらの申請書又は届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、一部をこれらの申請書又は届出書のいずれか一通に添付するものとする。
(指定の基準等)
第一条の二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 (以下「令」という。)第一条 の規定による指定(第一条の八までにおいて単に「指定」という。)は、指定を受けようとする特定講習団体(社団法人全日本ダンス協会連合会(昭和六十年五月三十日に社団法人全日本ダンス協会連合会という名称で設立された法人をいう。)又は財団法人日本ボールルームダンス連盟(平成四年三月二十四日に財団法人日本ボールルームダンス連盟という名称で設立された法人をいう。)をいう。以下同じ。)の申請に基づき行うものとする。
2 国家公安委員会は、前項の規定による申請に係るダンス教授講習(ダンスの教授に関する講習をいう。以下同じ。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その指定をしなければならない。
一 ダンスを有償で教授する能力を修得しようとする者を対象とするものであること。
二 その内容が、ダンスを有償で教授する能力を有する者を養成するために必要な技能及び知識の向上を図る上で、適正かつ確実であると認められること。
三 その実施に関し、適切な計画が定められていること。
四 当該講習における指導に必要な能力を有すると認められる者が講師として講習の業務に従事するものであること。
五 全国的な規模においておおむね毎年二回以上実施されるものであること。
(指定の申請)
第一条の三 指定を受けようとする特定講習団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 ダンス教授講習の名称
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 ダンス教授講習の実施の基本的な計画を記載した書面
二 講師の氏名、住所並びにダンス教授講習に関する資格及び略歴を記載した書面
(名称等の公示) 第一条の四 国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けたダンス教授講習(以下「指定講習」という。)の名称並びに当該指定講習を行う法人(以下「ダンス教授講習機関」という。)の名称及び住所を公示するものとする。
(名称等の変更)
第一条の五 ダンス教授講習機関は、前条の規定により公示された事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
2 国家公安委員会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示するものとする。
3 ダンス教授講習機関は、第一条の三第二項各号に掲げる書面の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
(国家公安委員会への報告等)
第一条の六 ダンス教授講習機関は、指定講習に係る毎事業年度の事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 ダンス教授講習機関は、指定講習に係る毎事業年度の事業報告書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。
3 国家公安委員会は、指定講習に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該ダンス教授講習機関に対し、その事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(改善の勧告) 第一条の七 国家公安委員会は、指定講習が第一条の二第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき又はダンス教授講習機関の指定講習に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該ダンス教授講習機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(指定の取消し等)
第一条の八 国家公安委員会は、ダンス教授講習機関が、この規則の規定に違反したとき、又は前条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、当該指定講習の指定を取り消すことができる。
2 国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
(推薦の方法)
第二条 令第一条の二 の規定による推薦は、特定講習団体が行うダンス教授試験(ダンスを正規に教授する能力に関する試験をいう。以下同じ。)であつて国家公安委員会が指定するものに合格した者について、その者の氏名、住所及び生年月日(以下「氏名等」という。)を記載した名簿を国家公安委員会に提出することにより行うものとする。
2 前項の規定によるほか、特定講習団体は、その者からの申出により、国際的な規模で開催されるダンスの競技会に入賞した者その他の前項に規定する者と同等の能力を有すると認められる者について、その者の氏名等及びその者が同項に規定する者と同等の能力を有すると認めた理由を記載した推薦書並びにその理由を疎明する書類を国家公安委員会に提出することにより、推薦を行うことができる。
(指定の基準等)
第二条の二 前条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)は、指定を受けようとする特定講習団体の申請に基づき行うものとする。
2 国家公安委員会は、前項の規定による申請に係るダンス教授試験が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その指定をしなければならない。
一 ダンスを正規に教授する能力を修得しようとする者を対象とするものであること。
二 ダンスを正規に教授する能力を有するかどうかを判定することを目的として行うものであること。
三 その実施に関し、適切な計画が定められていること。
四 当該試験における判定に必要な能力を有すると認められる者が試験員として試験の業務に従事するものであること。
五 全国的な規模においておおむね毎年一回以上実施されるものであること。
(ダンス教授試験への準用規定) 第二条の三 第一条の三から第一条の八までの規定は特定講習団体が行うダンス教授試験について準用する。この場合において、第一条の三第二項中「前項」とあるのは「第二条の三において読み替えて準用する前項」と、同項第二号中「講師」とあるのは「試験員」と、第一条の四中「指定講習」とあるのは「指定試験」と、「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、第一条の五第一項中「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、「前条」とあるのは「第二条の三において読み替えて準用する前条」と、同条第三項中「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、「第一条の三第二項各号」とあるのは「第二条の三において読み替えて準用する第一条の三第二項各号」と、第一条の六中「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、「指定講習」とあるのは「指定試験」と、第一条の七中「指定講習」とあるのは「指定試験」と、「第一条の二第二項各号」とあるのは「第二条の三において読み替えて準用する第一条の二第二項各号」と、「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、第一条の八第一項中「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、「前条」とあるのは「第二条の三において読み替えて準用する前条」と、「指定講習」とあるのは「指定試験」と読み替えるものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第三条 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第一号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
一 申請書 第一条の三第一項
二 ダンス教授講習の実施の基本的な計画を記載した書面 第一条の三第二項
三 講師の氏名、住所並びにダンス教授講習に関する資格及び略歴を記載した書面 第一条の三第二項
四 事業計画 第一条の六第一項
五 事業報告書 第一条の六第二項
六 名簿 第二条第一項
七 推薦書及び推薦の理由を疎明する書面 第二条第二項
八 申請書 第二条の三において読み替えて準用する第一条の三第一項
九 ダンス教授試験の実施の基本的な計画を記載した書面 第二条の三において読み替えて準用する第一条の三第二項
十 試験員の氏名、住所並びにダンス教授試験に関する資格及び略歴を記載した書面 第二条の三において読み替えて準用する第一条の三第二項
十一 事業計画 第二条の三において読み替えて準用する第一条の六第一項
十二 事業報告書 第二条の三において読み替えて準用する第一条の六第二項
2 前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下単に「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
3 第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。
一 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
4 第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
5 第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 提出者の名称
二 提出年月日
(客席における照度の測定方法)
第四条 法第二条第一項第五号 の客席における照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める客席の部分における水平面について計るものとする。
一 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
二 前号に掲げる場合以外の場合
イ いすがある客席にあつては、いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
(国家公安委員会規則で定める遊技設備)
第五条 法第二条第一項第八号 の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。
一 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
二 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
三 フリッパーゲーム機
四 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
五 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備
(客の依頼を受ける方法)
第六条 法第二条第七項第二号 の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。
一 電話その他電気通信設備を用いる方法
二 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項 に規定する信書便
三 電報
四 預金又は貯金の口座に対する払込み
五 当該営業を営む者の事務所(事務所のない者にあつては、住所)以外の場所において客と対面する方法